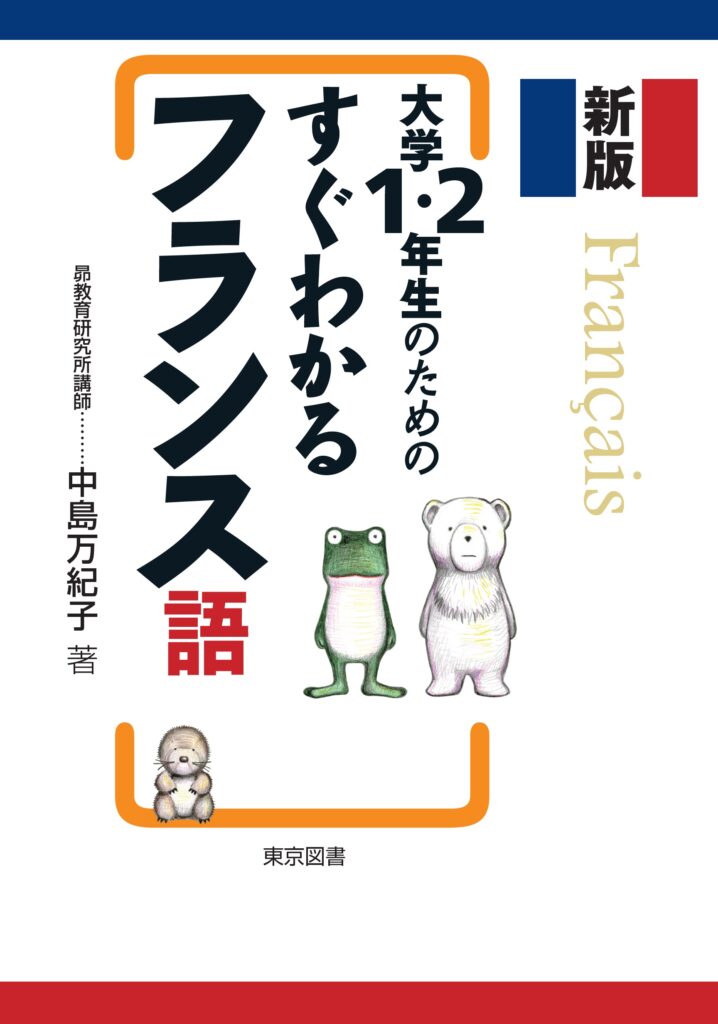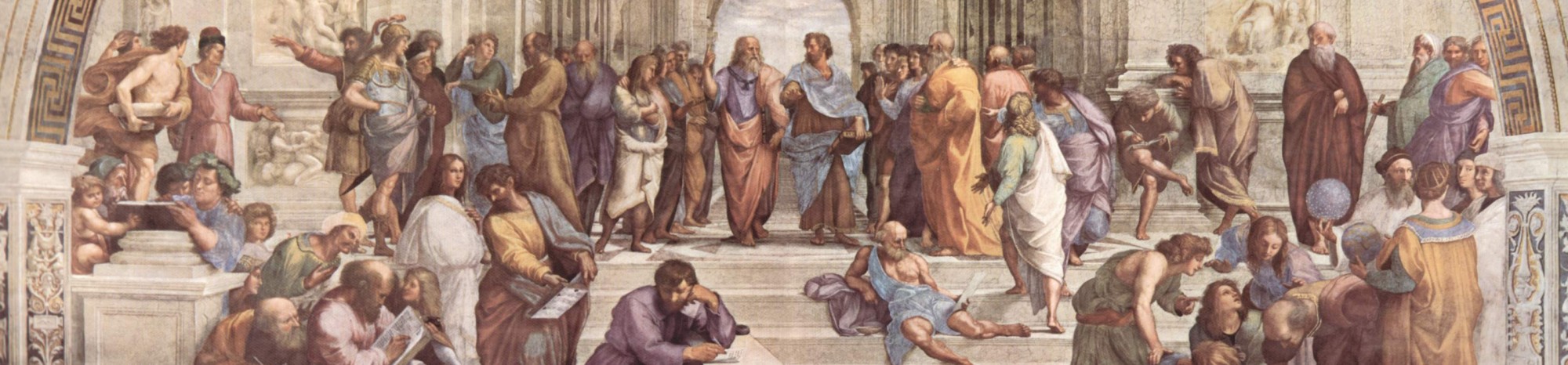東大大学院 総合文化研究科の合格者の方からまたまた合格者の声をご投稿いただきました。一言一句変えず、掲載いたします。
―――
外部大学から企業就職、退職後に東大総合文化への進学です。同じ条件の方の参考になれば。
【入塾を決めるまで】
大学院の受験を考え始めたのは、受験年度の8月初め頃でした。一次試験が翌1月末~ですから、期間は約半年。受験勉強や退職に伴う手間を考えると、仕事を続けるか進学するかの判断だけは急がねば、という心持でした。
ただ、東大以外の大学出身ということもあって、志望した総合文化研究科のことも当初はよく分かっていませんでした。とりあえず文学部(人文社会系)の過去問を買ってきたものの、自分の行きたい専攻のページがなく、呆然としてしまったことをよく覚えています。総合文化の過去問もようやく生協の通販で購入できましたが、中を読んでみて英語も第二外国語も意味がほとんど取れず、専門科目の論述に関しては何をどう書けばよいのかも分からない状態でした。
ようやく自習ではどうしようもなさそうだ、と気づいて書店やインターネットで情報を集めていたところ、この昴のホームページにたどり着きました。今ご覧いただいている皆さんと同じように合格者の声を読んでいるうちに、「これなら…!」となり、さっそく面談の機会を設けていただきました。
面談でお会いした高橋先生(この後ずっとお世話になるわけですが)は当初、英語の先生とうかがっていましたので、持ち込んだ卒論をお見せしたところ、論文の分野の専門知識や考察、疑問点などをすらすらと、まるで湯水のように、挙げられていて大変に驚かされました。塾の先生は受験のテクニックを教えるもの、との思い込みがあったので、個別の研究範囲にまで踏み込んで親身にお話ししてくださるのは、とても新鮮に感じました。
くよくよ色々と考えていたのが、この面談で退職、入塾、進学まで一気に踏ん切りをつけられたのは気持ちとして大きかったです(9月から入塾、有給を消化して9月末に退職)。
もし、入塾するかどうかお悩みのようでしたら、まず面談で雰囲気を確かめてみる、というのもいいかもしれません。私がお会いした感触では、ですが、最初の面談の時の先生の話しぶりや論文への指導の仕方は、その後の講義や論文添削の雰囲気とおよそ一緒のものでした。
【塾でのこと、試験対策について】
〇英語
総合文化の英語は英→日訳と日→英訳の記述問題がメインなので、地道に「読んで訳す」をひたすら繰り返すのが一番の近道のように感じます。ただ、出題される文章が人文系の背景知識を必要とするものが多く、倒置や省略など文法の理解もかなり問われるので、単語を何となく訳出して出来上がった文章が正解とかなりかけ離れている、ということがままあります。
高橋先生は『詳解 大学院への英語』という「院試ど真ん中」な本の著者でいらして、上述の背景知識や文法の説明も講義で豊富に取り扱ってくださいます。また、毎週の演習の授業で生徒たちの解答を細かく添削して返してくださるので、訳出にあたってどこに気をつけるべきかのポイントが段々と分かっていくようになります。
私自身、講義の回数を踏んでいくうちに、着実に実力が伸びていく感覚がついてきました。この時期に学部でお世話になった教授に英語の訳文を見てもらう機会があったのですが、「卒業してからかなり英語論文を読み込んだみたいだね、力がついている」と褒めていただいて大層嬉しかった記憶があります。
大学院では英語論文は嫌でも数を読みこなしていくことになるでしょうから、長文を読むことへの抵抗感は試験前に失くしてしまった方が「お得」な気がします。私は怠惰な性格なので、昴でコンスタントに英語の難しい文章に取り組む環境を用意してもらったことは大助かりでした。
〇第二外国語
中国語選択なので昴の二外講座は利用していません。参考書メインの自宅学習でした。
ただ、昴で学んだ英語の対策と重なるところも多かったです。例えば、試験で出題される中国語文には日本語との同型同義語(日本語と同じ意味・かたちの単語)がなまじっか多く、何となく単語の意味をたどると「こなれた」訳ができてしまう罠があるように感じました。昴で「こなれた訳よりも、まずは正確な訳をつくる」という意識を養っておいたおかげで、個々の文法事項で点数を落とさずに済んだように思います。
出てくる単語・文法のレベルは私の体感でHSKの4-5級くらいでしょうか。中国の近代政治史をざっと復習しておくと、出題の内容理解がだいぶ捗るのでオススメです。
参考書はかなり探しましたが、東方書店『長文読解の“秘訣”』と荒川清秀『一歩すすんだ中国語文法』が長文訳という出題の性質と合っていてよかったです。『長文読解』の方は高橋先生の『大学院への英語』と構成が似ていて一緒にまわしやすいです。あと猫が可愛い。
〇専門科目・論述
これが一番苦戦しました。私も、読んでいただいている皆さんも「書く」こと自体にはあまり抵抗がない部類だと思いますが、与えられたお題を元に、決められた時間で、まとまりのある文章をつくる、という作業には一定の訓練が必要な人がほとんどではないでしょうか。
特にお題に関しては、専門分野の幅広い範囲から複数題が出されます。解答の自由度はかなり高めですが、課題文が提示している問題の背景知識を押さえておいた方がより「間違いがない」のは確かです。書く能力に加え、卒論の範囲から外れた広い知識を詰め込んでいくことも重要になってきます。
私も、昴の初回の演習では50分で書くべきところを90分の演習時間を丸々かけて、書きたいことの半分も書けなかった苦い経験があります。ですが、何回か講義と演習を繰り返していくうちに、見よう見まねでなんとか時間内に収まるようになっていきました。
演習では提出した論述にびっしり添削がついて返ってきますし、講義では各々の受講生が解いた問題の解説を聞くことができます(プライバシーにはかなり気をつけられています)。当然、他の専攻や人文社会系など別の領域の講義を受けることになりますが、無駄な感じはまったくしません。むしろ、論述問題は課題文にアプローチできるカードをどれだけ持っているか、という勝負でもあるので、隣接分野にも飛びついてみる姿勢をとった方がうまくいくと思います。講義中に先生から薦められて読んでみた書籍に、実は自分の研究論文にかかわるテーマが含まれていた、という経験も何度となくありました。シンプルに、講義を聞いていると好奇心がわいて楽しい、というのが一番のおすすめポイントかもしれません。
〇二次試験対策
二次試験は面接形式ですが、事前に提出する研究論文がとりわけ重視されます。自分の研究の出来そのものが問われる機会、と言っても良いかもしれません。
私は既卒の立場ですので、卒業論文を一度書き上げている分、内部生より楽ができたのは確かです。一方で、院の先輩や助教、教授の方々に気安く相談できる環境からは離れてしまいました。大学図書館も在学中よりかなり使用が制限されます。「院試は情報戦」とよく聞きますが、一人ごり押しで立ち回れる自信は自分にはありませんでした。
その点で、昴で先生から、論文のアドバイス、過去問の閲覧、参考図書の貸し出し等々、様々な形でご助力いただいたことは大変に励みになりました。どうすればこの研究がより面白くなるか、実のあるものにできるか、というところまで親身に考えてくださるのは、研究室のどれほど親しい先輩であってもなかなか難しいことではないでしょうか。面接で問われるのも、つまるところは研究が修士や博士論文まで耐えうるかどうか、というところに集約されるようなので(個人の感想です!)、先生と相談しながら研究の今後のビジョンを見据えておくのも大事な試験対策になった、と思っています。
――
最後に、若い時期に社会人から大学院に入ろうとする(私のような)人間にとって、大学院入試は結構な負担になると思います。大学受験のような統一模試がないので、現時点でライバルがどれほどいるのか、どれくらい勉強がデキて、その中で自分がどれほどの立ち位置なのか、といった情報がまるでわからないままに会社を辞める決断をしないといけません。独学する場合、参考書もかなり限られて手探り状態のスタートです。いくつかの候補の一つとして、大学院の専門塾に入って経験豊富な先生のもとで学ぶ、という選択肢は十分検討する価値があるものだと思います。少なくとも私は、昴に入って良かったと切に感じています。
長々とご覧いただき、ありがとうございました。皆さまのこれからの研究生活が実り多きものになりますよう、心よりお祈り申し上げます。
―――
(以上、いただいた「合格者の声」です。)
東大総合文化研究科、合格者の方の別の体験記です。あわせてご参照ください。
東京大学 総合文化研究科・京都大学 文学研究科・早稲田大学 文学研究科合格体験記
東京大学 総合文化研究科合格体験記 1
東京大学 総合文化研究科合格体験記 2
東京大学 総合文化研究科合格体験記 3
東京大学 総合文化研究科合格体験記 4
東京大学 総合文化研究科合格体験記 5
東京大学 総合文化研究科合格体験記 6
東京大学 総合文化研究科合格体験記 7
東京大学 総合文化研究科合格体験記 9
東京大学 総合文化研究科合格体験記 10
東京大学 総合文化研究科合格体験記 11
「合格者の声」一覧のページと、昴のトップページのリンクは以下です。
合格者の声一覧
昴教育研究所トップページへ戻る